先輩の退職から3か月。
院内の空気が少し落ち着いた頃、「新人2人の指導をお願いしたい」と院長に頼まれた同僚がいました。
給料が変わらないのに責任が増える現実、限られた時間の中で求められる成果。
その話を聞きながら、歯科衛生士という仕事に求められる“信頼”と“負担”の重さを改めて感じました。
院長からの指導依頼|断れない現場の空気感
相談してきたのは、歯科衛生士5年目の同僚でした。
これまで新人教育を担当していた先輩が退職して3か月、院内のバランスを取るために、院長から「新人2人の指導をお願いしたい」と頼まれたそうです。
経験年数が増えると、自然に「中堅」扱いされ、育成を任されるのは避けられない流れかもしれません。
厚生労働省の統計によると、歯科衛生士の平均勤続年数は約7年。
つまり、現場では5年目あたりが「教える側の適齢期」になるのです。
ただ、同僚にとっては「給料は変わらないのに責任だけ増える」「自分もまだ教わる立場なのに」という複雑な思いがあり、返事をする決心を鈍らせていました。
指導係を受けるメリットとデメリット
まず、受けることによるメリットは「信頼の証」として院長からの評価が高まる点です。
責任ある立場を引き受けることで、昇給や役職手当につながるケースもあります。
医院によっては、スタッフミーティングの発言権が広がったり、患者対応の裁量が増えるなど、自分の存在価値を再認識できる機会にもなります。
一方で、デメリットも現実的です。
院長への報告日誌の提出が義務づけられ、帰宅時間が30分ほど遅くなることも。
残業手当は数百円程度にとどまり、時間と労力のバランスに悩む人も多いでしょう。
さらに、後輩がうまくいかない時に、「教え方が悪い」と言われるなど、精神的なプレッシャーを感じることもあります。
教育担当は、指導だけでなく“人間関係の潤滑油”としての役割も担うため、気配りの負担が増すのも事実だと思います。
とはいえ、こうした経験は将来のキャリア形成に直結します。
教育力やコミュニケーション能力は転職時の面接でも高く評価されるスキルです。
短期的には大変でも、中長期的には「人を育てる力」が自分の武器になる可能性があります。
現場で無理なく続けるための工夫
指導係を続けるうえで大切なのは、「一人で抱え込まない」ことです。
教育計画や進捗管理を一人で背負うと、心身の負担が増え、結果的に職場全体の雰囲気にも影響します。
日本歯科衛生士会では、院内でのメンター制度や定期面談の導入を推奨しています。
後輩への指導内容を共有したり、他のスタッフと協力しながらチームでサポートする体制を整えることで、負担はぐっと軽減されます。
また、厚労省の指針では、教育や研修に関わる時間も「業務の一環」として扱うべきとされています。
勤務時間内で実施できるよう院長に相談したり、就業規則の見直しを提案するのも建設的な方法です。
まとめ|「選ばれた理由」を前向きに受け止めて
指導係を任されるのは、単なる「人手不足の補填」ではなく、あなたの経験と人柄が信頼されている証です。
もちろん、負担は増えますが、その分だけ自分の成長を実感できる場でもあります。
教えることで得られる気づきは、実践や臨床技術だけでなく人間的な幅を広げてくれます。
少しずつでも前向きに、後輩と一緒に成長していけたら理想的ですね。
もし今、戸惑いや不安を感じているなら、「なぜ自分が選ばれたのか」を思い返してみてください。
その理由の中に、きっとあなた自身の強みが隠れています。

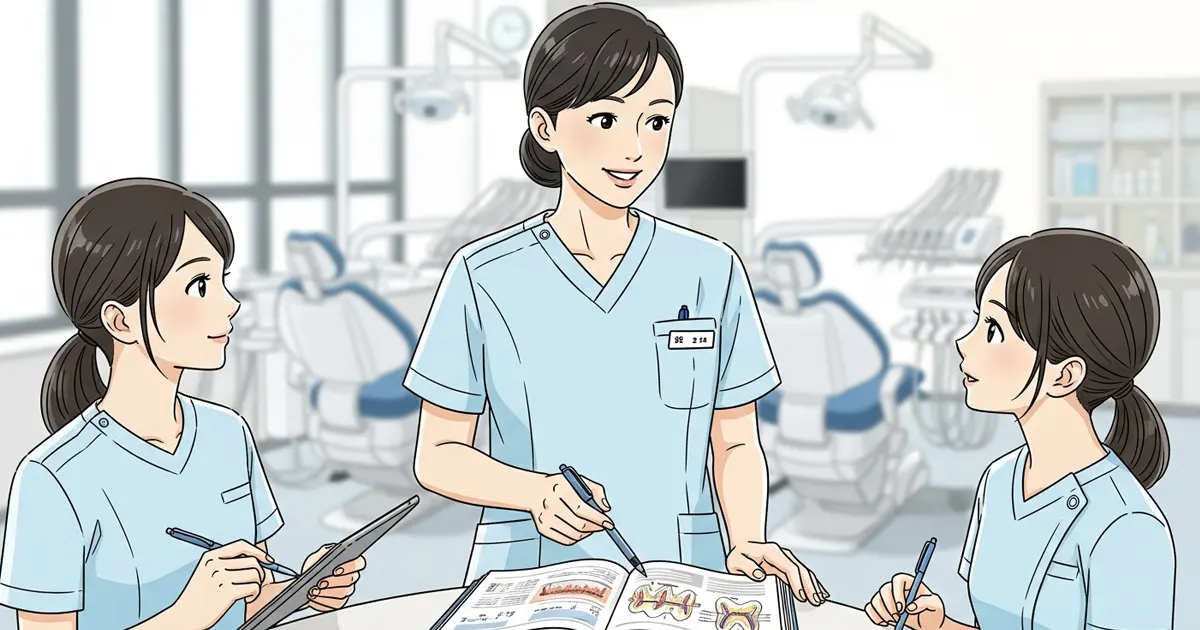
コメント